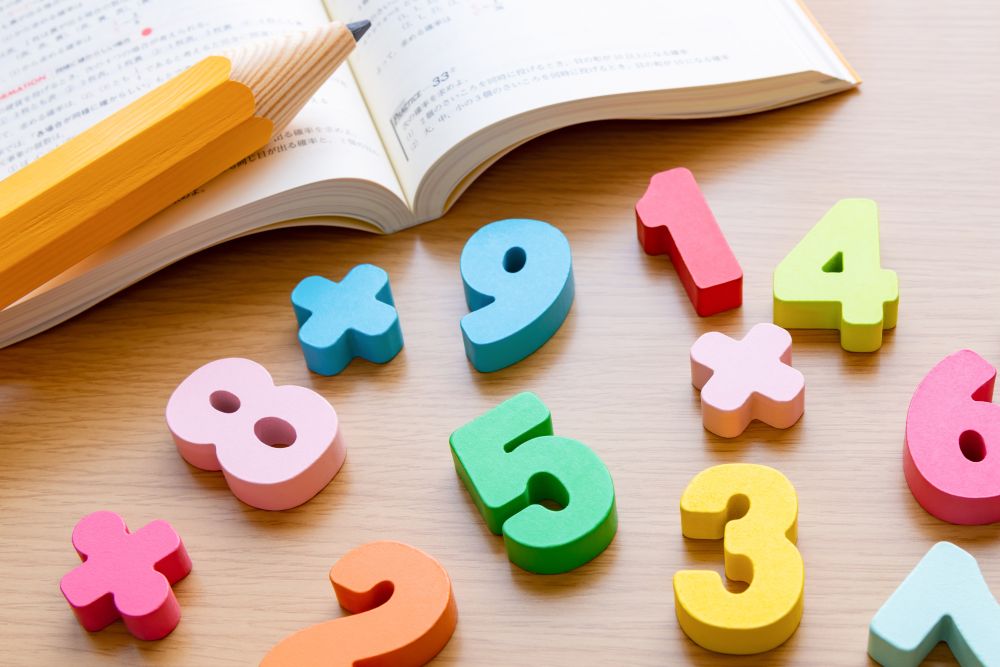小学校のプログラミング教育にも役立つ知育おもちゃとは?種類や選び方は?

小学校でも導入されたプログラミング教育にそなえたいと考える方も多いのではないでしょうか。
ここでは楽しみながら自然にプログラミングを学べる知育おもちゃの種類や選び方、遊びながら身に付くチカラについて詳しくご紹介します。
プログラミングおもちゃってどんなもの?
プログラミングおもちゃの特徴や、さまざまな遊びを広げられるおもちゃについてご紹介します。
プログラミングで必要な力を養える知育トイ
プログラミングおもちゃとは、プログラミングで必要な「問題解決能力」や「諦めずやりぬく力」などを養える知育トイです。
使いこなすためには、頭で考えたことやイメージしたことを実際に形にしていく作業が必要となります。形にしてイメージと違う場合には、思い描いた形に近づくように、試行錯誤や工夫をこらすのです。
プログラミングおもちゃはこのように遊びながら、さまざまな能力を鍛えることができる知育トイといえます。
プログラミングおもちゃの種類
プログラミングおもちゃには、定番のものから最新のものまで色々な種類があります。
- ブロック

- さまざまな形や大きさのものを組み立てて遊びます。作り上げる形に正解はなく、シンプルな形から複雑な形まで、イメージによって色々な完成形を作ることができるのが魅力です。
「このブロックに乗せたらどうなるのだろう」「〇〇を作るにはどうしたらいいのだろう」などと、自分で考え工夫しながら楽しむことができます。
- パズル

- 各パーツを当てはめていく作業を繰り返します。ひとつのパーツを当てはめるには上下左右のパーツの形、組み合わせ方を考慮しなければなりません。
当てはめた形が違うこともあり、試行錯誤をしながら完成形を目指す、プログラミング的な思考が育ちます。
- ボードゲーム

- サイコロやカードを使うボードゲームも、同じ動作や処理を繰り返し行います。
思いがけない失敗や想定外の出来事への対処法を考えながらゴールを目指すことで、問題解決能力を養うことができます。
- ロボット
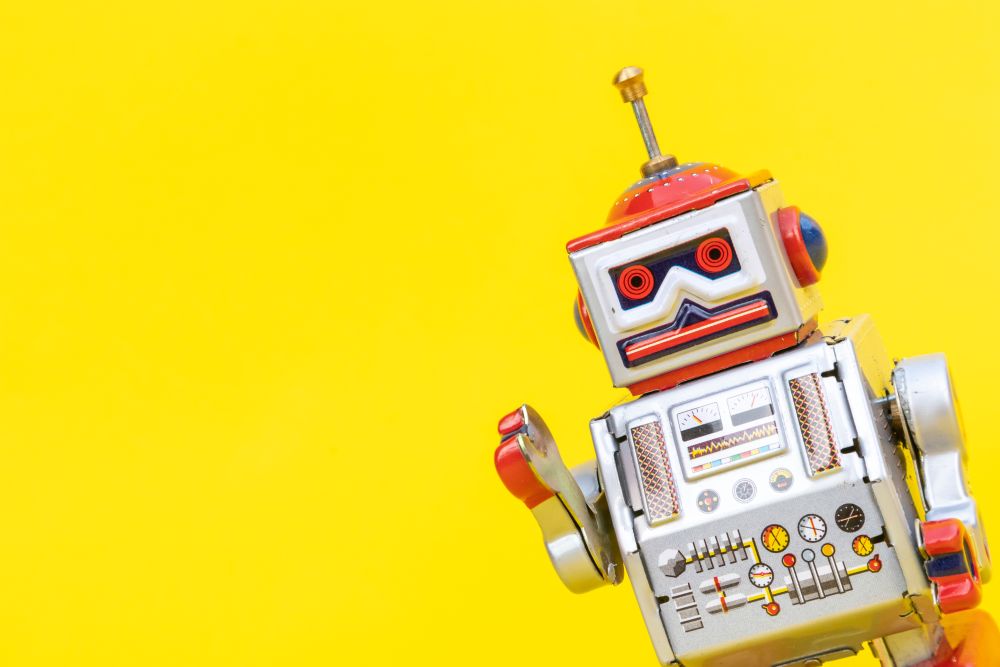
- ロボットタイプのおもちゃは実際にさまざまなパーツを組み立てて、さらに自分で動かすことができます。トライアンドエラーを繰り返しながら、指示通りに動くように工夫する力が身につきます。
- ゲームアプリ

- 決まった指示どおりにアプリ上のキャラクターを動かす、ゲーム感覚で楽しめるものもあります。
マインクラフトやロブロックスは、素材を集めて建物を作ったり、敵と戦ったりすることができます。自由な発想で遊びながら試行錯誤する中で、創造性や発想力を育むことができます。
- スモールキューブ型ロボットトイ「toio(トイオ)」

- toio(トイオ)はキューブ型をしたコンパクトなロボットトイです。ブロックや手作りの作品を乗せる、組み立て変形させて自由自在に動かすなど、遊び方は子どもたち次第で無限に広げることができます。
年齢やレベルに合わせ、初級から上級までさまざまな遊びを楽しみながら、プログラミングを学べます。
おもちゃで身につく論理的思考

プログラミングおもちゃでは「論理的思考が身につく」といわれますが、具体的にどのようなことなのでしょうか。
論理的思考とは
物事を順序だてて整理できることを論理的思考といいます。
論理的思考が身についていると、問題や課題に直面したときに筋道を立てて起こったことを整理し、理解することができます。問題解決の糸口を導き出しスムーズに対処するためには、論理的思考が必要です。
例えば問題が仕事上で問題が起こった場合、論理的思考が身についていれば、問題の結果と原因の関連をとらえ「なぜこのような結果が出たのか」「どうすれば解決できるか」などとを順序だてて効率的に考えることができます。
これを小学生や中学生に当てはめると「なぜ忘れ物が多いのか、どうすれば減らせるか」「友達とケンカになるのはなぜか、どうしたら仲直りできるか」など、生活の中でも論理的思考は様々なシーンで役に立つと考えられます。(とはいえ、頭で理解してもなかなか実行にうつせないのが実情ですが・・・)
プログラミングおもちゃで論理的思考が育つメカニズム
コンピューターや機械は自分で勝手に動くことはできません。指示によってしか動かず、より正確に動かすためには、複雑で細かな指示が必要です。
例えば目的地にたどり着くために、「右に曲がる」「まっすぐ進む」という単純な指示では思い通りに進まないことがあります。「〇番目の信号を右に曲がり、突き当りを左折する」など、より細かい指示であるほど正確性が高まるというわけです。
またコンピューターや機械は間違った指示では間違った動きをするため、問題が発生した際には「指示が間違っているかもしれない」と原因を突き止める必要があります。
曖昧な指示では動かないため、論理的思考を育てるには、原因と結果の関係が明瞭なプログラミングを用いたおもちゃや道具が適しているといえます。
飽きずに遊んで学べるプログラミングおもちゃの選び方

ここからは、プログラミングおもちゃの選び方について詳しくご紹介します。
子どもの興味関心や得意なことで選ぶ
プログラミングおもちゃを選ぶ際には、子どもの興味や関心に合わせることが大切です。
例えば音楽に対する反応がよい、歌うのが好きという子には音楽創作ができるおもちゃがおすすめです。
また、もともとブロックの組み立てや作品作りが好きな子は、パーツを組み立てて動かせるロボット創作キットを候補に挙げることができるでしょう。このように子どもの興味や得意なことに合わせて選ぶのもポイントです。
年齢で選ぶ
プログラミングおもちゃを選ぶ際には、対象年齢を確認しましょう。各年齢の発達段階や学習能力などに応じ、適したおもちゃを選ぶことが大切です。
対象年齢別の特徴と選び方のポイントをみていきましょう。
- 幼児(3~5歳)
- 幼児期はひらがなやカタカナ、数字を少しずつ読めるようになる時期ですが、まだ個人差があります。文字が読めない場合でも楽しめるのがブロックやパズルなどのおもちゃです。
ブロックやパズルはパーツが細かいものも多いため、誤嚥しないサイズを選びましょう。親子で楽しめるボードゲームやバランスゲームもおすすめです。
- 小学校低学年(6~7歳)
- 小学校低学年になると、文字や数字が読めるようになります。そのためパソコンやスマートフォンで子ども向けのゲームアプリを楽しむことができます。
- 【おすすめ】Scratch Jr(スクラッチジュニア)、Viscuit(ビスケット)
- 小学3~4年生(8~9歳)
- 小学校3、4年生になると漢字やアルファベットの読みも上達してきます。パソコンやタブレットなどでワンランク上のゲームアプリを楽しむのもおすすめです。
またロボットで実際にプログラミングして動かすなど創作系のおもちゃにも挑戦することができます。
【おすすめ】Minecraft(マインクラフト)、Roblox(ロブロックス)
- 小学校高学年(10歳~)
- 高学年ではプログラミング言語を用いたロボットやプログラミングで音を作り、楽器のように演奏できる創作キットなどもおすすめです。
理解力が上がるため、より複雑で難易度の高いおもちゃにも挑戦できます。
【おすすめ】SongMaker(ソングメーカー)
まとめ
プログラミングおもちゃであれば、強制しなくとも自然と遊びながらプログラミング的思考や論理的思考を身に付けることができます。子どもの年齢や発達、好みやおもちゃの種類に応じて、ぜひ子どもに合ったおもちゃを選んでみてください。
小学生・中学生のためのプログラミングスクールをお探しなら
プログラミングを楽しく学ぶコースも充実しているスタープログラミングスクールなら、小学1年生から受講できます。ICTリテラシーに加えて「コミュニケーション力」や「チームワーク」など、AI時代に活躍するための「21世紀型スキル」を伸ばす学びを実践しています。
ご興味のある方は、無料体験でお子様と一緒にぜひ体験してみてください!
この記事の監修者

-
スタープログラミングスクール コラム編集部
私たちは、これからのAI時代を生きる子ども達には「自分で考えるチカラ」が必要と考え、プログラミング教育を通してその力を養うお手伝いをしています。講師、教材開発、広報など様々な担当者で構成されたコラム編集部が、現場での感覚や実例も交えて、子育て中の方に役立つ情報を分かりやすくお伝えしていきます。